「LED照明は、建築物のためのものではない。人間のためのものだ」。米Human Centric Lighting Society(HCLS) でExecutive Directorを務めるJohn Hwang氏は、こう指摘する。その意味をかみ砕けば、「照明設計を行う際に、効率だけを求めるのではなく、人間工学的メリットを考えた照明を設計し、精神科学とビジネスをマッチングすることである」ということだ。
LED照明は明るさの競争から、次の市場価値を見いだすための新しい闘いに移ろうとしている。それを強く実感したのは、2014年4月にドイツで開催された照明関連で世界最大級の展示会「Light+Building2014」を訪問した際のことだ。
Hwang氏の指摘は、この方向性を示したものである。実は、欧米では人間中心の照明を「Human Centric Lighting(HCL)」と呼び、それを具現化するための業界団体が立ち上がっている。同氏が属するHCLSは、その代表例の一つだ。
2014年10月15日~17日にHwang氏は来日し、パシフィコ横浜で開催された「LED
Japan2014」で講演した。冒頭の言葉は、講演後のインタビューで語ってくれたものだ。「固体照明技術が進歩し、光の『非視覚的効果』の研究成果が積み重ねられたことによって、照明ソリューションに応用可能な研究開発分野に新たな可能性が開かれた」と同氏は加えた。「これからのLEDは、可視光以上の価値がある。それは、照明が人に語りかけるというものだ。健康な生活を送ること、幸せな日々を過ごすことを支援するテクノロジーの一つであり、照明にとってとても重要な時期にきている」(同氏)。

■大きな関心を集める「第3の視細胞」
例えば、目には視覚機能と強く関連しない光受容体、ipRGC(intrinsically photosensitive retinal ganglion cell:内因性光感受性網膜神経節細胞)が存在する。これの細胞は、錐体細胞、桿(かん)体細胞に続く光受容細胞として第3の視細胞と呼ばれており、今後の照明開発の研究対象と一つとして大きな関心を集めている。人間が持つ約24時間周期の生体リズム「サーカディアンリズム」にも強く関与していると見られているからだ。
HCLSが指摘したipRGCの非視覚的作用は、大きく5つある。(1)瞳孔径の収縮、(2)松果体のメラトニン生成抑制、(3)心拍数と深部体温の上昇、(4)コルチゾールとセラトニンへの刺激、(5)神経生理学的な刺激薬としての作用である。これらの作用は、反応時間の短縮や注意欠如の低減、覚醒の向上などにつながっていると見られているという。例えば、聴覚はボディバランスを整える機能を持っていると言われている。これと同じように、視覚も単に見るだけではなく、様々な機能を持っているのだ。
一般に人間が明るい場所で最も強く感じる光(最大視感度)の波長は555nm。つまり緑色の領域だ。一方、米ハーバード大学メディカルスクールのSteven W. Lockley氏によれば、サーカディアンリズムへの作用が最大となるのは青色領域の波長である460nmであるという。
■体が覚醒と睡眠を自然と行える環境を整える
HCLSでは現在、プロスポーツの施設、医療機関、学校、企業オフィスなどと共同で光の「非視覚的効果」に関する複数の実験プロジェクトを進めている。
NASA(米航空宇宙局)との共同研究では、宇宙空間でのLED照明の効果について実験中だ。宇宙では昼も夜もないため、光のリズムを調節することでサーカディアンリズムを強化し、宇宙飛行士の宇宙での滞在を支援している。光を用いて覚醒させる際には青色光を比較的多く含む6500Kの色温度の光を用いる。その後、4500Kの光の中で過ごすことにより、身体が覚醒と睡眠を自然なサイクルで行える環境を整えられるという。
光の利用は、世界の都市生活者の生活を変えることにもつながるとHwang氏は話す。例えば、米国のシアトルは曇りがちの天候で有名だ。HCLSによれば、年間226日間は曇りがちで、そのうち155日間は雨。晴天は58日間だけという。日光を浴びる機会が少ないため、寝不足が多いのではないかと考えられている。同氏は、「シアトルではスターバックスコーヒーの売り上げが高いが、それは昼間の覚醒が弱く、そのためではないか」と、冗談交じりで語る。
実は、都市によって夜の景色の色合いも異なる。シアトルはアンバー系の色で、ソウルはブルー系の色なのだという。ソウルでは夜、自宅に帰っても色温度の高い青色の光が強いため、眠れないのではないかとHCLSは考えている。脳を活性化させるために青色光は好ましいが、夜遅くまで使用すると不眠の原因となる可能性がある。そのため、シアトルのように太陽光を浴びる機会が少ない地域、ソウルのように1日中青っぽい光に包まれた都市では、自然と調和した照明色を選ぶことが有用ではないかと考えている。

■日光に近いLED、術後の回復に期待
LED照明は、その色による医療への応用も期待されている。例えば、英国の医療関連の学術誌「Journal of Royal Society of Medicine」で1998年に発表された研究では、脊髄手術を受けた患者の術後の回復期で日当たりのいい病室とそうでない病室について比較した結果がある。それによれば、日光が当たる平均の明るさが46%高い日当たりのよい病室では、鎮痛薬の使用率が特に女性で約22%少なかったという。
こうした研究成果から、日光をきちんと浴びることが術語の回復で有用であるとの見方が強い。このため、太陽光に近いLED照明を採用することで、ストレスの減少やより早い回復、手術後の痛みの軽減といった効果に期待が集まっている。
■選手の故障を低減し、コンディションを維持
HCLSでは、「グリーンスポーツアライアンス」という研究グループでスポーツ関連の研究も進めている。119チームが所属する同アライアンスではスポーツチームのための冊子を発行しており、その中でLED照明に関する研究結果をまとめている。
HCLSでは、LED照明がスポーツ選手の故障率の低減やコンディションの維持に活用できるとみている。例えば、相対色温度6500Kの照明は興奮しやすい光で、うまく使えば集中力を高める効果があるという。
米国のプロアスリートの平均年俸は200~400万米ドルで、プロチームの年間給与総額は6000~2400万ドルだ。年間における選手の負傷・故障率は20%前後にも上っており、これが低下すれば、各チームにとってのメリットは大きい。
実際、実証実験の結果を基に野球の米大リーグ(MLB)の「シアトルマリナーズ」が拠点とするスタジアムのクラブハウスとトレーニングルームの照明をHCLの考え方に即したLED照明に取り換えた。HCLSは、シアトルマリナーズが導入したLED照明の投資を2年程度で回収できるとみているという。
LED照明は、米国のプロスポーツ選手を悩ます移動による時差の問題にも効果があるという。米国ではプロアメリカンフットボール「NFL」のレギュラーシーズン中、月曜日の夜に「Monday Night Football」と呼ばれる試合が定期的に開催されている。この試合では、西海岸のチームが勝利することが多いという。HCSLでは、その大きな理由が西海岸と東海岸の時差にあるのではないかと見ている。
米国の西海岸と東海岸には3時間の時差がある。このため、西海岸で午後6時に試合開始する場合、東海岸の選手の体は午後9時の状態にある。このような選手のコンディションの違いが試合結果に影響しているためではないかというわけだ。LED照明を活用して選手のコンディションを試合開始時刻に合わせてピークにもっていくことができれば、選手の最大のパフォーマンスを引き出すことができるというわけだ。
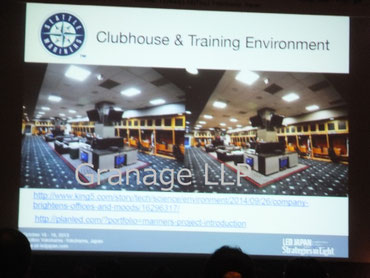
■照明で労働環境を整える
HCLSでは、こうした医療分野やスポーツ分野での成果を今後、一般の企業や学校、家庭に応用していきたいと考えている。
例えば、オフィスビルや工場などにHCLの考え方に基づいたLED照明を導入するメリットは大きい。
3万人が働くような巨大ビルに導入することを想定した場合、もちろん省エネ効果だけでも2~3年で投資を回収でき、年間の省エネ効果は約500万米ドルになるという。さらに、労働環境を変えるメリットがある。例えば、HIDランプやハイベイライトの下でのノイズや、夜間勤務者を照らす光を改善すれば、雇用者の生産性や欠勤の改善につながるとみている。この改善効果は年間4920万米ドルに達するとHCLSは試算している。つまり、HCLの考え方に基づく照明は、普通の省エネに比べ10倍のコストメリットがあるというわけだ。
こうした実験や研究の成果を見ると、LED照明の使い方はまだ十分とは言えないのかもしれない。照明環境は、視覚的に感じるものに加えて生理的な作用をきちんと検討することで付加価値はさらに高まる。照明の機能として人の睡眠、覚醒、神経への影響などを考慮することの必要性は高まっている。単なる「あかりとしての照明」の枠を超えて、人間工学や生理学を応用した要素技術を組み合わせることで、その存在感を強めていくことになるだろう。
もちろん、HCLの取り組みには課題もある。例えば、HCLの定義そのものには、まだあいまいな点も残る。光の人体への作用メカニズムも不明な部分は多く、実験によるデータをこれまで以上に充実させる必要性もあろう。ただ、HCLの考え方に基づいた取り組みは照明業界で重要なキーファクターになりそうだ。LED照明はこれからさらに多様な分野の知見や技術を取り込み、今後人間の生活環境を豊かにしていくものになることは間違いない。


